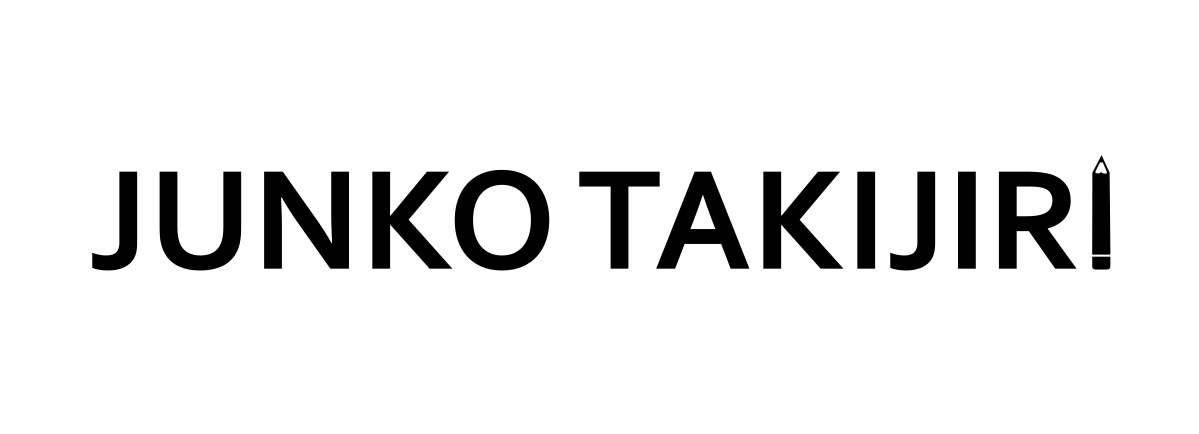著者:内田樹
出版社:文藝春秋
発行日:2002年6月20日
形態:新書
『読むことの可能性』で、ロラン・バルトを読みたかったことを思い出した。構造主義からポスト構造主義に位置する作家と言われているので、入門書として手に取った。バルトは構造主義者と呼ばれることを拒んだそうだが、便宜上、私も入り口にさせてもらう。
著者は、フランス現代思想の専門家。難しい言葉で論を積み上げて、読者を置いてけぼりにするのではなく、小気味よい語りを読者のほうを向いて展開し、同時代人として問いを共有してくれる。この「入門者のための、平易に書かれた構造主義の解説書」も、いつもの内田先生という感じだ(2002年の本だけど)。
私がめざしているのは、「複雑な話」の「複雑さ」を温存しつつ、かつ見晴らしのよい思想史的展望を示す、ということです。
構造主義という思想がどれほど難解とはいえ、それを構築した思想家たちだって「人間はどういうふうにものを考え、感じ、行動するのか」という問いに答えようとしていることに変わりはありません。ただ、その問いへの踏み込み方が、常人より強く、深い、というだけのことです。ですから、じっくり耳を傾ければ、「ああ、なるほどなるほど、そういうことって、たしかにあるよね」と得心がゆくはずなのです。なにしろ、彼らが卓越した知性を駆使して解明せんとしているのは、他ならぬ「私たち凡人」の日々の営みの本質的なあり方なのですから。(p.15)
つくりとしては、「構造主義とは何か」が明示されている箇所はなく、代表的な思想家と、その関連、考えを理解するときの勘所やキーワードを解説していく形をとる。知りたければ、他の本を読んでおいたほうがいい。以下は『読むことの可能性』(pp.117-118)からの抜粋。
構造主義
・1950~1960年代。1960年代後半から70年代に英米へ輸入された際、「構造主義」と呼ばれるようになった。
・ソシュールの言語理論の影響を受けて、構造主義の言語学概念を社会・文化現象に応用した、主にフランス思想家の活動のこと。
・目標:無意識的に動いている「構造」(言語、精神、社会の構造)を分析して記述すること。再構成を目指す。
・功績:人間はある構造に組み込まれ、縛られている。それは人間の自由や自律性がかなり限定的であるということを意味すると同時に、そうした構造があるからこそ、ものを見たり、考えたり、意味づけたりすることが可能だということを、徹底的に掘り下げたこと。
例えば文学研究なら…
構造主義発生前までは→作品の新しい解釈を生み出す。
構造主義では→作品がいかにしてその意味や効果を持つのかを理解しようとする。何が文学作品を可能にする約束事なのかを考える。
(*手段としては、二項対立を重要視する。二項対立のほころびに気がつき、二項対立崩しで構造主義を批判する試みがポスト構造主義。構造主義者かつポスト構造主義者と呼ばれる人がいるのは、構造主義を突き詰めていった結果、自分でその問題に気づき、思想を批判的に更新していったから。私はこの流れがとても好き。)
『寝ながら~』に戻る。以下は、おもしろくて特にノートにまとめなおしたところ。
第1章 構造主義前史
構造主義に影響を与えた、マルクス、フロイト、ニーチェについて。前史から話を始めるのが新鮮だった。私の、マルクスへの印象は、長いこと「読んでみたい」と「難しそう」の行き来で終始していたのだが、サルトルが思想的に依拠したとか、バルトも初期に影響を受けたというのを知ると、少しかじるくらいはしたいと思った。ニーチェの系譜学的思考の箇所では、「いま・ここ・私」が共感できるか否かで良し悪しが決まるような現代のウェブコンテンツのあり方や、「いま・ここ・私」の正しさを前提として、内省を自らに向けないまま、正否や善悪の議論っぽいことで盛り上がるようなSNSの流れを思いながら、学ぶべき姿勢として読んだ。ニーチェは「なんでこんなに人間は馬鹿になったのか」を突き詰めた先で「超人思想」に行く。この点に理解はできるが、私は支持しない。
ニーチェはもともと古典文献学者としてスタートした研究者です。古典文献学という学問はその研究者に特殊な心構えを要求します。それは、過去の文献を読むに際して、「いまの自分」の持っている情報や知識をいったん「カッコに入れ」ないといけない、ということです。そうしないと、現代人には理解も共感できないような感受性や心性を価値中立的な仕方で忠実に再現することはできないからです。
ニーチェは異他的な精神の活動に偏見ぬきで共感する能力を、おそらく古典文献学を通じて体得したのだろうと思います。(pp.41-42)
第2章 ソシュール
構造主義の思想的な父。言語学。昔勉強したはずだが、おぼろげ。要復習。
マルクスが記述したような資本主義の危機に直面しなくても、あるいはフロイトが例に挙げたような神経症を患っていなくても、ただ、ふつうに母国語を使って暮らしているだけで、すでにある価値体系の中に取り込まれているという事実をソシュールは私たちに教えてくれたのでした。(p.72)
第3章 フーコー(社会史)
何が語られるかよりも、何が語られてこなかったかを問う。ニーチェの系譜学的思考を受け継ぐ。
第4章 バルト(文学・文化研究)
記号学の用語の説明は、今まで読んだ本の中でいちばんわかりやすかった。例がいい。シニフィアン、シニフィエに対する「将棋を指していて、歩をうっかり失くしてしまった時に、みかんの皮を代用する」話や、エクリチュールに対する「俺という一人称を使い始めると、ことばづかいだけでなく、生活習慣も集団的な暗黙のルールに影響されるので、それまで着ていたクマちゃんのパジャマをもう着れなくなる」話など。
第5章 レヴィ=ストロース(人類学)
フィールドワークで非西洋の民族と深く接していたことで、西洋的知性の「思い上がり」を批判。サルトルの実存主義が廃れたポイントが理解できた。「主体が、与えられた状況において自己形成していく」という考えは実存主義も構造主義も同じだが、実存主義が政治と絡むと、構造主義が批判を始めることになる。マルクス主義とハイデガーの存在論で武装したサルトルを、レヴィ=ストロースは西洋的な思い上がりとして咎めた。これが致命傷になり、実存主義は衰退。
第6章 ラカン(精神分析)
フロイトの考えを支持し、深く突き詰め、発展させた功績で知られる(そのためか、この章はフロイトの話が多い)。私は心理学や精神分析があまり好きではないのだが、言葉、対話、物語への考え方は興味深く読んだ。
精神分析では、「自我」は治療の拠点にはなりません。(・・・)精神分析が足場として選ぶのは、「ことば」の水準です。「対話」の水準、あるいは「物語」の水準と言ってよいかも知れません。(p.173)
意外に思われるかも知れませんが、精神分析的対話は、被分析者が「ほんとうに体験したこと」や「ほんとうに考えていること」を探り当てるためになされているのではありません。いくら語っても、おのれの中心にある「あるもの」に触れることができないという構造的な「満たされなさ」から被分析者は決して逃れることができないからです。被分析者が語っているのは「空語」です。全力を尽くして、被分析者は自分について語っているつもりで、むなしく「誰かについて」語っているのです。「その誰かは、被分析者が、それこそ自分だと思い込んでしまうほど、彼自身に似ている」だけなのです。
しかし、それでいいのです。どれほど「漸近線」な接近に過ぎなかろうとも、「自我」について語ることによって、被分析者と分析家のあいだで創作され、承認された「物語」の中での「私」という登場人物はどんどんリアリティを増していくからです。被分析者は語ることを通じて、分析家との「あいだ」に架橋された構築物の上にその主体性の軸足をシフトしていきます。精神分析的対話とは、いわば被分析者の「本籍」を、彼の「内部」から、分析家と被分析者が両者の中間にある中空に共作しながら構築している「物語」の内部へと移す、「戸籍の移転」に類する作業なのです。
症状は、患者の内部にわだかまる「何か」が「別のもの」に姿を変えて身体の表層に露出した、一つの「作品」です。同じように、被分析者が語る「抑圧された記憶」もまた、一つの「作品」です。ですから、この「戸籍の移転」は「あるつくりもの」を「別のつくりもの」に置き換えることに過ぎません。しかし、それでも、ある病的症状がより軽微な別の症状に「すり替え」られたとしたら、それは実利的に言えば、「治療の成功」と言ってよいのです。それが「無意識的なものの代わりに意識的なものを立てること、すなわち無意識的なものを意識的なものに翻訳すること」というフロイトの技法なのです。(pp.179-180)
そういえば、結局線を引きながら、余白に書き込みながら読んだので、寝ながらは学べずじまい。