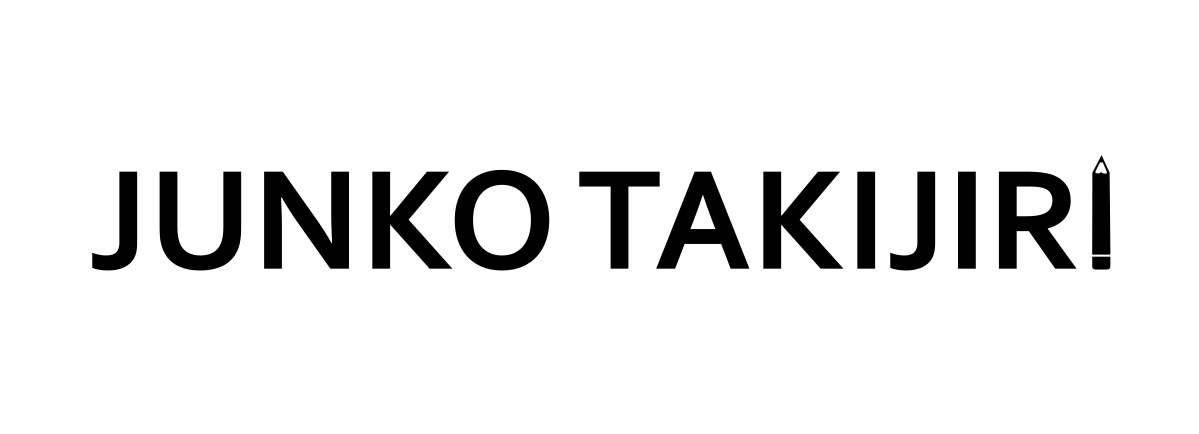著者:サイモン・ウィンチェスター
訳者:鈴木主税
出版社:早川書房
発行日:2006年3月31日
形態:文庫
THE PROFESSOR AND THE MADMAN
A Tale of Murder, Insanity, and the Making of the Oxford English Dictionary
by Simon Winchester
1998
Oxford Endlish Dictionary、通称OED。
編纂主幹のジェームズ・マレーと、篤志文献閲覧者のウィリアム・チェスター・マイナーを軸にまとめられた、辞書制作話のノンフィクション。
16世紀のイギリスには、今でいう辞書にあたるものがなかったらしい。
聖書を読むためのラテン語辞書、単語リストのような本、難解語や専門用語を集めた本はあったが、日常語から難解語までを網羅し、かつ意味、発音、綴り、用例を説明するものはなかった。
p.122
「英語辞書」は、今日の一般的な意味、つまり英語をアルファベット順に並べてその語義を記したものという意味においては、比較的新しくつくられたものだ。400年前には、そのような便利な書物は英語については存在しなかった。pp.126-127
シェークスピアの時代には定義はなく、こういう言語であると、「固定」されてはいなかった。英語は空気のようなものだった。そこにあるのが当然とみなされ、すべてのイギリス人を包みこむ特徴となっていた。だが正確に言うとどんなものなのか、どういう要素で構成されているのかは、誰にもわからなかった。
用例を実際の文献から引っぱってきて並べることで、単語がどんな変化を経て現在に至るかを示すOED。
編纂リーダーのマレーが収録語を列挙し、ボランティアの協力者を募った。
協力者は指定された本を読み、どんな語がどういう意味で使われているかを探し、カードに書き写し、マレーに贈る。
編纂チームはそれをカテゴライズし、精査し、辞典のページに入れていく。
総収録語数414825、養成1827306、総ページ数16570、全12巻の辞典は、70年をかけて手作業でまとめられた。
この途方もない作業に、人一倍熱心な協力者として参画したのがマイナー。
ありあまるほどの知識、意欲、時間、書物をもって貢献した。
話をドラマティックにするのは、マイナーが精神疾患を抱えていたこと、それゆえの殺人を犯した過去があること、「女王陛下の思し召しのあるまで」、つまり無期で、精神病院に収監されていたこと、この事実をマレーが編纂開始後の数年間知らずにいたことである。
マイナーには、母国アメリカで軍医として働いた経験があった。
高い地位、教育、収入があるうえに、自殺企図や暴力への傾向がなかったことから、ある程度の快適さを許され、他の収監者とは違う待遇を受けられた。
OEDに収録された用例のうち、数万はマイナーによるものだというから、マイナーが精神を病み、罪を犯して収監されていなければ、辞書はできあがらなかったのかもしれない。
この本にはマイナーの精神に影が差すに至った悲しい経緯や、収監中の様子についても丁寧に記されている。
無期の隔離の中、彼が自分にぴったりの仕事を見つけたときの描写は輝いて見える。
p.198
社会の一員になりたいと長いあいだ望んでいながら遠ざけられていた彼は、その社会からやっと会員バッジを送られたように思った。規則を記したこの文書を送られたことによって、自分が実社会の片隅にふたたび受け入れられたと感じた。実社会とはかけ離れた精神病院の二部屋の独房におかれたままなのはたしかだが、学問の世界との確固たるつながりをつくり、もっと快適な現実世界との関係を築いたのだ。p.206
彼の本と、そのなかから言葉を見つける仕事が、新しく選択した人生の中心になろうとしていた。これから二十年間、自分の本と、そこに書いてあることと、そのなかの言葉の世界に没頭し、頭脳を酷使すること以外、彼はブロードムアでほとんど何もしなくなるのだ。
この本は1998年に出版され、2006年に邦訳化、2019年に映画化された。
日本での公開は2020年で、観に行きたいと思っていたが、コロナの影響で足が重く、諦めた。
いつか配信で観たいと思っているものの、本のほうを先に読んでよかったと思う。
本は次のような献辞に始まり、あとがきで終わる。
G・Mを偲んで
pp.326-327
この奇妙な物語のなかでいちばん悲劇的な人物は、最も忘れられがちな男であり、1872年2月の土曜日の夜に銃で撃たれ、ランベスの丸石を敷きつめた湿った冷たい舗道に倒れた男である。
この物語のなかで最も悲劇的に結びついている二人の主人公を追悼するものといえば、みすぼらしく目もあてられないありさまだ。ウィリアム・マイナーの質素で小さな墓石はニューヘヴンの共同墓地にあり、ごみとスラム街に囲まれている。ジョージ・メリットの墓には何もなく、南ロンドンの無秩序な墓地に灰色がかった草が生えているだけだ。だが、マイナーは大辞典の仕事をしたためにいくらか優位に立ち、その仕事が彼の記念として最も長く残ると言えるかもしれない。しかし、マイナーが殺した男が記憶に値することを示唆するものは、まるで何も残っていない。ジョージ・メリットは完全に無名の男になってしまったのだ。
だからこそ、120年以上経ったいま、このささやかな記述は彼に捧げる言葉で始まるのが適切だと思われる。そして本書が故ジョージ・メリットが生きたことへの小さな証として書かれたのも、そのためだ。メリットの不幸な死がなければ、これらの出来事は決して起こらず、この物語を語ることもできなかったのである。
殺人者が辞書の編纂に関わっていたこと、言葉を愛するふたりが友情をはぐくんだことは、たしかに映画化が好まれそうな、メディア受けしそうなものだ。
事実が明らかになった当時も、センセーショナルに扱われた。
著者のサイモン・ウィンチェスターは、経緯のドラマティックな部分を認めながらも、できるだけ広い視野で目配りし、筆致が暴動しないように気をつけながら書いていると思う。
ゴシップ的な盛り上げよりも、(辞書制作の話にわざわざ興味をもつような)読者の知的好奇心を刺激するネタを入れたり、書き方を工夫したりしている。
学ぶものが多くある本。