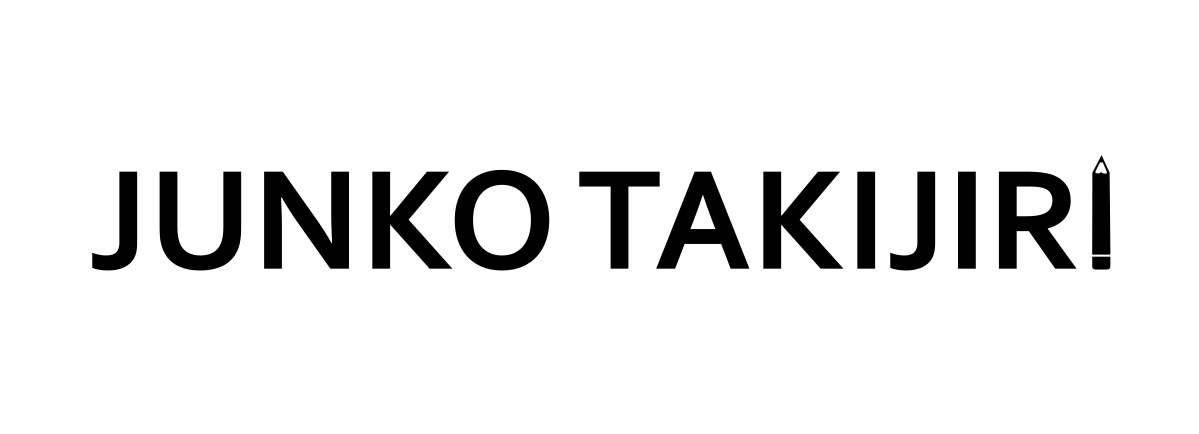訳者:古川綾子
出版社:晶文社
発行日:2017年12月15日
形態:単行本
달려라, 아비
by 김애란
2005
最近、少しずつ韓国文学を読むようになった。何気なく手に取ったキム・エラン『外は夏』がきっかけ。9つの作品からなる短編集。どれも、「何かを探しても見当たらない」話だなあと思った。
「走れ、オヤジ殿」
母子を置いて消えた父。母子のために走ったことなどなかった父。ある瞬間、あることのためだけには、必死で走った父。子である語り手は、父がランニングに出かけただけだと考えて、記憶の中で父を走らせ続ける。母譲りのユーモアで生い立ちや出来事を語る。手紙をきっかけに現れる感情。ユーモアが転化したような嘘。
p.17
父はランニングをするために家を出た。私はそう信じることにした。戦地に赴いたわけでも、他に妻を求めたわけでも、どこかの国の砂漠に石油パイプラインを埋めに行ったわけでもないのだと。ただ、家を出るときに時計は持っていかなかったようだと。
p.29
でも父はまだ、私の頭の中を走っていた。あまりに長いこと想像してきたから、うまく消せないようだ。だが突然「自分は結局、許せないから想像してきたのではないか」という気がした。父を走り続けさせる理由は、父が足を止めた瞬間、自分が父に駆け寄って殺してしまいそうだったからではないのか。不意に悲しみがやってきて、その悲しみが自分を欺く前にさっさと眠ってしまわなければと思った。
「走る」イメージを使ってこんなふうにまとめあげられるのがすごい。
「コンビニへ行く」
家の近くにコンビニが3軒ある。あるコンビニで商品を買う。たいてい決まった時間なので、店にはたいてい同じ店員がいる。通い続けると、自分がどんな商品を使って生活しているのかが知られてしまう。店員が親しみのある関係を築こうとして(あるいは単なる興味本位からかもしれないが)、話しかけてくるようになる。学生さんですか? どこの大学? 専攻は?
それが嫌になり、行きつけの店を変える主人公。しばらくするとそこではそこで、店員との別の居心地の悪さが出てくる。もう一度店を変える。今度の店のスタッフは話しかけてこない。話しかけてこないがゆえに、起こること。
人を「知っている」とはどういうことか。
p.53
私は想像する。ある日、三つのコンビニが向かい合う道路の真ん中で女が車にひかれて死ぬ。三店の店長、つまり証人たちは彼女のことを「知っている」と証言するが、全員が異なる陳述をする。コンビニの店長たちは食い違う陳述の中で自身の記憶を疑い、今度は彼女のことを「知らない」と否定する。では三つの否定の中で、そのとき女はどうなって誰になるのか。
p.63
年中無休のその場所で私は―私に必要なものをわかっているふりをしてくれるその場所で私は―そういうわけで誰とも会わず、誰とも抱きしめ合わない。
「彼女には眠れない理由がある」
不眠症の女性の話。眠れない理由について延々と。眠れない理由を話すことが、過去のできごと、現在の生活の様子、思考のくせ、人間関係を描きだす。おもしろいつくりだ。
「永遠の話者」
主に3つの文型、「私は〇〇である」「あなたは〇〇である」「○○であればいいのに」で構成される、ある女性のモノローグ。「私」といいつつ、幽体離脱して「私」を観察しているような感じ。哲学的な問答みたいでまどろっこしいが、「私」のわからなさは、わかるような気がする。
p.147
私は私がどんな人間なのか、たびたび想像する。私は私からあなたと同じくらい離れているから、私がいくら私だと言っても私を想像するしかない人だ。私は私が想像する人、でもそれが私の姿であることが不思議で、しきりにあなたの想像を借りてくる人だ。
「愛の挨拶」
昔、父親が消えた経験をもつ男性。「父親に捨てられた」のではなく、「父さんが姿を消した」「父さんが道に迷ったみたい」という表現をする。「姿を消したと思ったら再び現れる者」のとしてのネッシーにときめく。水族館勤務。「無数の父さん」という表現よ。
p.157 ネッシー出現のニュースを観たときのシーン
ふと、僕は気になった。「そういえば、地価の洞窟に暮らしていた彼が、どうしてまた急に白頭山にやってきたのだろうか? それも湖じゃなくて休火山のてっぺんに・・・・・・?」。僕はネッシーの痕跡だと主張されている、二メートルほどの水しぶきをしばらく見つめた。すると一つの確信が生まれた。僕は告白された人のように、急に恥ずかしくなった。つまり彼は・・・・・・僕に会いに来たのだ。自分の姿がテレビを通して全国に放送されるであろうことを知り、僕に挨拶をしに来たのだ。特に目的はない。たった一度だけの挨拶。愛の挨拶をしに来たのだ。「私はここにいる。ずっとここにいたんだ。でも、これは二人だけの秘密で、私はまた姿を消すから・・・・・・」。つぶさに見ると、水しぶきはネッシーがヒレをなびかせたときに作られたような形をしていた。僕はヒレがないから黙って手を振った。
p.164 テレビで「ナショナルジオグラフィック―深海の神秘編」を観たときのシーン
僕は昔、ネッシーをはじめて見たときとはまた違う興奮を感じていた。人間がそもそも海から這い出てきた存在だということとは別に、ただそれらが大昔からそこに「いた」という事実が驚くべきことだった。そこにいる彼らと、ここにいる僕が、その時間に会っているということ。海から出てきた人間が自分たちの技術を利用して、再び海に潜り、あるで夢を見ているかのように―自分の横を泳ぎ去っていく無数の父さんに会うということ。それは本当に驚異的な出来事だった。僕は遊園地で失踪した父さんが、もしかしたらあの中にいるかもしれないと思った。
「海辺でやたらと花火を上げるのは誰だ」
父さんと子の会話を中心にした、ほほえましい話。食堂でフグ鍋を食べながら、父さんは息子に、フグの毒の話をする。
pp.181-182
「お前は今晩、寝たらダメだ。寝たら死ぬ」
(・・・)
「父さんは?」
「父さんは大人だから大丈夫だ」
からかいを信じた息子は、眠たくならないように、父さんに髪を切ってもらおう、何か話をしてもらおうと決める。自分がどうやって生まれたのか尋ねる。父さんは「母親に聞くもんだ」と言うが、母さんは死んでしまっている。「どうやって?」としつこくせがむ息子に、父さんは母さんとの馴れ初め、二人の時間の記憶を話し始める。
父さんと母さんが出会ってしばらくして、仲間と海で遊んでいたとき、砂に埋められて、砂像にされて、下半身部分に花火をつけられたときのこと。
pp.193-194
ぽん! ぽん! 花火が花開く。父さんは横たわったまま、花火の洗礼を受ける。ぽん! ぽん! 満開の花火が美しい。こうして父さんの巨大な性器から打ちあがった花火がタンポポの綿毛のように夜空に広がっていったとき、父さんの光輝く種たちが孤独な宇宙へと遙か遠くに放射されたとき。
「ちょうどそのとき、お前が生まれたんだ」
カミソリで襟足を剃り終えた父さんが言った。しばらくじっと座っていた僕は父さんに向かって言った。
「嘘だ」
父さんと母さんがいい雰囲気になったとき、父さんは急に口臭が気になりだす。「ちょっと待って」と席をはずし、口をゆすぐけど、まだ気になる。石鹸を見つけて、とっさに指につけ、歯を磨く。
p.205
何度ゆすいでも、石鹸の味は消えない。むかむかして吐きそうだ。石鹸のにおいで頭が割れそうに痛む。まるで自分の脳が石鹸でできているような気分だ。父さんはふらつく脚に力を込め、再び母さんのもとへ走っていく。
「お待たせしました」
「どこへ行ってきたんですか」
「何でもないです」
父さんは頭がずきずきする。でも母さんの顔を見た瞬間、裸足で熱い砂を踏みしめたときのように全身が痺れてくる。父さんは思わず唇を舐める。この世で最も重要な嘘でもつくかのように父さんは唇を舐める。父さんが母さんの肩をつかむ。母さんが目を閉じる。そして、二人の顔が徐々に近づく。二つの唇が合わさる直前。世界の。静寂。そして長いこと待ちに待った口づけ。二人の唇が重なり合う。その瞬間、父さんの頭上に数千個のシャボン玉が一斉に昇っていく。ふわふわ。宇宙に放射される父さんの夢。そして透明なシャボン玉が昼間の夢のように広がっていったとき。爽やかなヴィノリア石鹸の香りが夜空へとゆらゆら青く広がっていったとき。
「ちょうどそのとき、お前が生まれたんだ」
僕は胸をどきどきさせながら叫んだ。
「本当に?」
父さんが淡々と答えた。
「嘘だ」
「紙の魚」
自分に関する物語を書くために、部屋の壁にポストイットを貼っていく男性。
p.231
ポストイットはすぐに壁の一面を埋め尽くした。
(・・・)
彼は後ろに下がると壁面を見つめた。自分の体にあれほど多くの物語が宿っているとは想像もしなかった。彼は最初の壁面と同じように、それらが「連結」しているという事実に驚いた。その当時は本当に何の意味もなかったり些細なことだったりしたのに、自分の人生に重要な影響を与えていたのだと気づいた彼は脅威を感じた。急に文章が浮かんできた。急いで彼はそれを他のポストイットに書き記した。
p.236
風が出たり入ったりするたびに、どの壁面も外に向かってゆっくりと膨れ上がり、またゆっくりと元の状態に治まった。そんなとき五つの壁面に貼られたポストイットは一斉にぶるぶると体を震わせた。するとそれは、より生きているように見えた。部屋全体が紙の鱗のついた一匹の魚になって、緩やかにこの世を泳ぎ回る想像をした。
海の砂が零れ落ちてきて、大きな魚が行ってしまったあと、足もとに飛んできたイチョウの葉っぱ。
「ノックしない家」
見知らぬ5人の女性が同居する家の話。不気味で怖いともとれるし、おもしろいなあと思えるし、よくわからなかった。こうだった可能性もある、ということの交差の結果なんだろうか。主人公が、他者の部屋に忍び込んで見たものも怖いけど、まず忍び込もうとしたところも怖い。