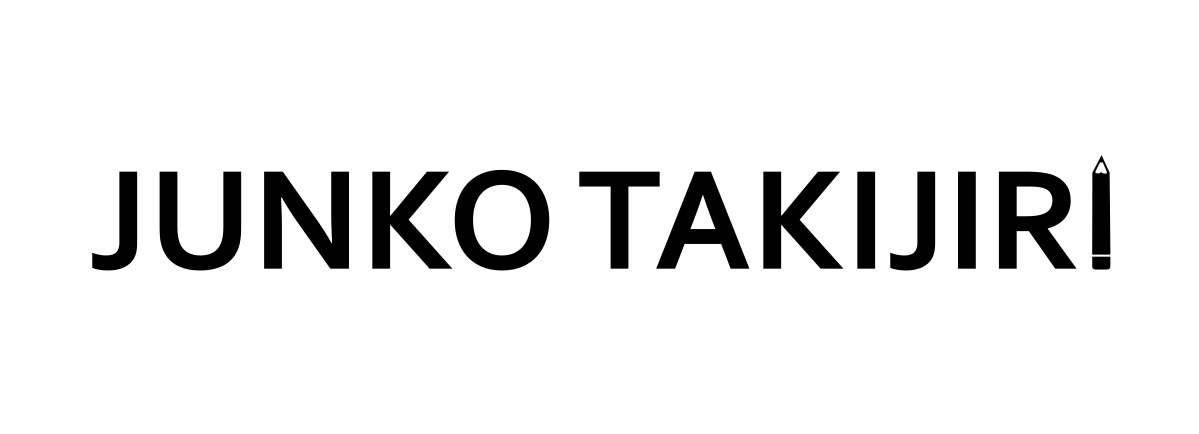著者:ペネロピ・フィッツジェラルド
訳者:山本やよい
出版社:ハーパーコリンズ・ジャパン
発行日:2019年3月1日
形態:単行本
The Bookshop
by Penelope Fitzgerald
1978
舞台は1950年代後半のイーストアングリア。交通手段を失った海辺の僻地、保守的な町、ハードバラ。戦時中に夫を亡くした中年女性、フローレンス・グリーンが、町で初めての本屋を開業する話。ささやかながらも自分の陣地と援軍を手に入れて、町の人々からの妨害、ねたみ、圧力に立ち向かっていく。
初読は退屈した。寒さが厳しい町の、閉鎖的で、陰鬱な話に感じた。会話の内容しかり、話の進み方しかり、遠回しの表現が多くて少し疲れた。たとえば敵対者とのやりとりを、弁護士を挟んだ皮肉たっぷりの手紙で続けるなど。
2回目は「階級」に注意して読んだ。
フローレンスは要するに、 “人間は絶滅させる者とさせられる者に分かれている、いかなるときも前者のほうが優勢だ” などというのは嘘だと思いこむことで、自分を欺いてきたのだ。いくら強い意志があっても、進む方向が定まらなくては役に立たない。いまのフローレンスはすっかり落ち込んでいて、戦う気力も湧いてこない有様だった。
ところが、意識の力が息を吹きかえした。三月末の火曜日の朝、わずか十分足らずのことだった。(p.51)
いくらラッパー(筆者注:買い取った古い家屋で起こるポルターガイスト現象のこと)や町の連中に妨害されても書店を開くのをあきらめたりするものですか、とフローレンスは心に決めた。(p.52)
新品の本は十八冊ずつ茶色の薄紙に包まれていた。整理を始めると、それぞれの社会的地位が自然に決まっていった。カントリーハウスをテーマにしたずっしりと重い豪華本や、サフォークの教会に関する本や、数巻からなる政治家たちの回顧録は、生まれながらの権利であるかのように表のショーウィンドーに並んだ。(p.57)
この本は伝統的にクラスが分かれていること、上層者が下層者を食いつぶす仕組みを前提にして書かれているし、フローレンスの挑戦も、そういう状況で「生き延びる」と腹を決めたところから本格的に始まる。
(茶会でブランディッシュ氏が言ったこと)「わざわざ美徳と呼ぶ必要もない美徳を、わたしはもっとも高く評価している。それは勇気だ。グリーンさん、あなたはその勇気をふんだんに持っている」(p.125)
フローレンスに勇気があるとしたら、その勇気は、例えば、非常時にも平常時にも同じ態度を貫くガマート将軍や、自分の世界が荒らされないように外の世界を締め出すブランディッシュ氏とは異なる形のものだった。フローレンスの勇気とは、結局のところ、生き延びようという決意に過ぎなかった。(p.135)
お金持ちの家柄、政治家、ホワイトカラーの人々は、倫理的・社会的な正しさを盾に共謀する。お金や名誉、権力、うぬぼれは、礼儀や思いやりと排他になるのがデフォルトなのか。個々の専門は違っても、権力者ガマート夫人を中心に動いているという点では、皆似かよった人たちだ。彼女に直接依頼されて動く者、文句を聞かされ、怒られないよう改善に動く者、喜ばせようと動く者、自覚していないが彼女の影響を十二分に受けて動く者。お金と名誉があり、かつ聡明で思いやりのある人は、ブランディッシュ氏しか出てこない。
階級が異なる人々、アウトサイダーは、階級に関する書かれ方が絶妙に異なる。ウォリーとクリスティーンは、当時のイギリスの子どもが階級を選ぶ唯一のチャンスだった「中等教育コース選別試験」(イレブン・プラス)を受験する年頃の子どもである(*)。一方はいい学校に受かり、同じ学校の子と付き合い始める。もう一方は落ちる。ある人は、これを「死刑宣告」とすら言う。
フリントマーケット・グラマースクールの合格通知は白い角封筒で届く。工業学校のほうは茶色の長封筒だ。最上級生の子たちは、その夏の朝、学校に着くと自分の机を見て封筒を目にし、一瞬にして自分の運命を知る。教室にいるほかの子供たちも同様だ。
ハードバラで生まれ育った子供たちは、いずれ長い人生をふりかえったときに、机の上で待っていた封筒以上に苦痛をもたらしたものや、運命を左右したものはなかったことを思い出すだろう。(p.153)
クリスティーンの母親、働き者のギップリング夫人は、娘がいい学校に入ってホワイトカラーの人と結婚するのをまず望む。望みが叶わなくても、「経験が糧になる」「何事にもマイナスがある」と考えられる。人への悪意は感じられない。今日も明日も畑のラディッシュに水をやる。育ちに応じて間引きしたり、肥料を与えたり、枯れても新しく植えなおすような、現実的で、とにかく次に進む人という印象。セオドア・ギルは、亡き妻のいとこの再婚により政治家とガマート夫人の遠戚になった、中年の自称画家。フローレンスの書店で個展を開きたいと強引に近づいてくる姿は、権力者と遠戚になったことで自分の階級が上がったのだと、うぬぼれているように見える。魚屋と洋装店のふたりは、自分からは動かず、繁盛している書店のおこぼれを待ち、手に入らなければねたむ人。
フローレンスは、妨害を受けながらも店を立ち上げ、営み続けた。ブランディッシュ氏は、限られた時間をフローレンスのために使った。クリスティーンは大人の客にも物怖じせず働き、意見し、フローレンスを支えた。勇気は、結果が成功に終わったから、成長できたから、ハッピーエンドになったから称えられるものではない。振り絞ったこと自体が、尊い。
結末としての希望や救いに言及がない物語だが、広く後世に読まれることを通じて「これはもう過去の話だ。世界はすっかり変わってしまった」と本棚の奥にしまわれる日が来るなら、あるいは語り継がれた先で、口承文学のように新しいバージョンが生まれるなら、それが何か実際の変化に寄与するなら、この本はオリジナルバージョンとしての役割のひとつを終えたと言ってもいい。その意味で、1978年の出版から40年近く経った2017年、ラストシーンを含め、随所に細かい改変を加えられ映画化されたことを、私は好意的に思った。
*イレブン・プラスについては、下記の文献を参考にした。
Lee, Hermione. 2013. Penelope Fitzgerald: A Life. New York: Random House.