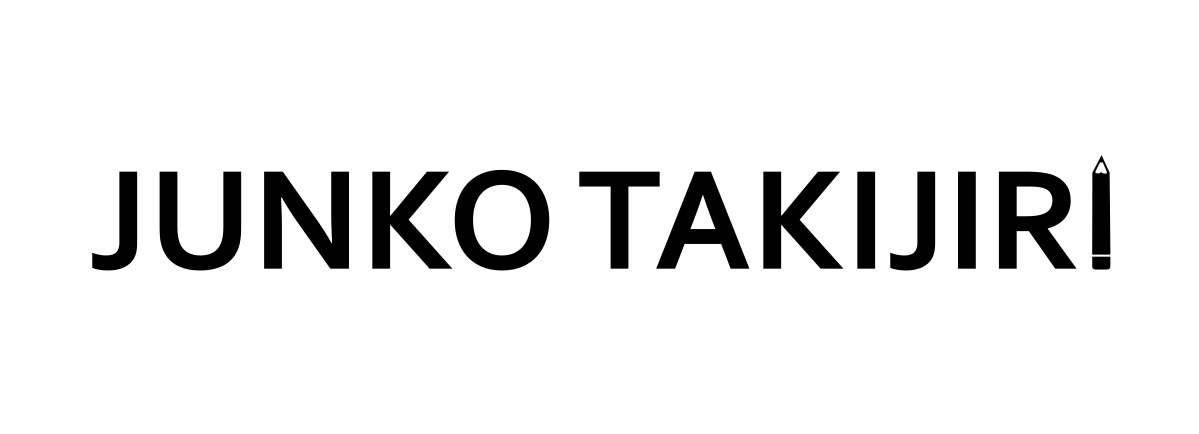著者:ジョン・ウィリアムズ
訳者:東江一紀
出版社:作品社
発行日:2014年9月30日
形態:単行本
Stoner
by John Edward Williams
1965
ある男が、英文学を志し、学問を探究し、教壇に立ち、友情を築き、結婚し、子を授かり、死ぬまでの話。
「美しい」と評されることが多い作品で、私も美しいと思ったが、何がどう美しいと思ったのかを知りたくて整理した。
————
(引用文中の下線は筆者による)
ミズーリ大学農学部2年生のストーナー。
実家の農場を継ぐ予定。
全学部制共通の必修教養科目、英文学の授業で人生が変わる。
英文学の教授、アーチャー・スローンが授業で取り上げた詩に心を奪われてしまう。
シェイクスピアのソネット73番(*)と、スローンの問いかけは、この本の基盤となる重要な箇所だと思う。
(*ソネットは14行詩のこと。14行のうち、4-4-4-2がそれぞれひとかたまり(=連と呼ぶ)。各行、最後の単語で韻を踏むのがルール。原文は中世英語で、abab cdcd efef ggのパターンで押韻する。73番は「老い」や「死」がテーマ。1連目は「晩秋~初冬」「廃墟」のイメージ、2連目は「夜」「闇」「眠り」のイメージ、3連目は「消えゆく残り火」のイメージ。)
かの時節、わたしの中にきみが見るのは
黄色い葉が幾ひら、あるかなきかのさまで
寒さに震える枝先に散り残り、
先日まで鳥たちが歌っていた廃墟の聖歌隊席で揺れるその時。
わたしの中にきみが見るのは、たそがれの
薄明かりが西の空に消え入ったあと
刻一刻と光が暗黒の夜に奪い去られ、
死の同胞である眠りがすべてに休息の封をするその時。
わたしの中にきみが見るのは、余燼の輝きが、
灰と化した若き日の上に横たわり、
死の床でその残り火は燃え尽きるほかなく、
慈しみ育ててくれたものとともに消えゆくその時。
それを見定めたきみの愛はいっそう強いものとなり、
永の別れを告げ行く者を深く愛するだろう
スローンは視線をウィリアム・ストーナーに戻して、乾いた声で言った。
「シェイクスピア氏が三百年の時を越えて、きみに語りかけているのだよ、ストーナー君。聞こえるかね?」
(・・・中略・・・)
「氏のソネットは何を意味するのだろう」
(pp.13-15)
スローンが順々に学生を指名していく中、ストーナーは他の学生同様、この問いに答えることはできなかったが、授業のあと、目に入る景色や自分の身体感覚に意識的になった。何かが変化した。
晩秋のうそ寒さが服の下までしみ通った。ストーナーはあたりを見回し、薄青い空を背にくねくねと立つ木々の節だらけの枝に目を向けた。次の授業へと急ぎ足でキャンパスを横切る学生たちが、そばをかすめて過ぎた。つぶやきの声と敷石を打つかかとの音が聞こえ、微風に向かって前かがみになった顔が冷気で紅潮しているのが目に入った。ストーナーはまるで初めての光景のように、好奇の目で同輩たちを眺め、とても遠くに、なおかつとても近くに感じた。自分も次の授業へ急ぎながら、その感覚を心に抱き寄せ、土壌科学の教授の講義のあいだも抱き続けた。
(p.16)
それまで自分のこと、将来のこと、人間関係、世界のことなどについて、あまり考えてこなかった、考えたくなかったストーナー。
学問への恋を知り、少しずつ、考えるようになる。
スローンと話した結果、英文学に転向し、教師になると決める。
「わからないのかね、ストーナー君? まだ自分というものを理解していないのか? きみは教師になるのだよ」
「恋だよ、ストーナー君」 興がるような声。「きみは恋をしているのだよ。単純な話だ」
(p.23)「きみは、自分が何者であるか、何になる道を選んだのかを、そして自分のしていることの重要性を、思い出さなくてはならん。人類の営みの中には、武力によるものではない戦争もあり、敗北も勝利もあって、それは歴史書には記録されない。どうするかを決める際に、そのことも念頭に置いてくれ」
(p.42)
師のスローンが見出し、導いてくれた学問への愛。妻への愛、娘への愛、友や同輩への愛に派生した。
うまくいくこともあれば、いかないこともあった。
期待が叶ったことも、叶わなかったこともあった。
我を忘れるほどエネルギーを感じる時期もあれば、敵意から攻撃され、大切なものを失い、無力感に苛まれる時期もあった。
長い教師生活の中で、好まれる教師像だったこともあれば、うとまれることも、周囲が無関心なことも、過度に攻撃されることも、伝説の人物のように伝承されることもあった。
ストーナーには祖先から受け継いだ知恵と倫理観があった。何があっても受け入れ、外から観察するような姿勢をとり、淡々と生きていく。
頭の奥深く、記憶のそのまた下層に、困苦と飢えと耐乏と痛みの知恵があった。ブーンヴィルの農場で過ごした幼少期を思い返すことはめったになかったが、意識の近くをいつも、祖先たちから受け継いだ知恵の血が流れていた。世に知られず、過酷で禁欲的な生活を送った祖先たちは、世間の抑圧に無表情で寡黙で険しい顔を向けることを共通の倫理観として貫いてきた。
(p.260)
愛と忍耐を行使する一方で、愛する人、もの、環境は徐々に奪われてしまう。期待した結婚生活や、書斎、家での居場所、娘を慈しむ時間を、イーディスが奪う。ウォーカーやローマックスからの敵意のせいで、大学のポストや授業を少しずつ失う。間接的な攻撃を受けた結果、キャサリンといちばん幸福だった日々を失う。年月や貧困で両親を、不況で義父を、戦争でデイヴィッド、教え子、婿、師を失う。自分の死の間際で、まだ生の世界にいるフィンチとの断絶をはっきりと感じる。
浮き沈みの中、もがきながら、ストーナーは自分自身になろうとした。自分自身であろうとした。学生のころは内省する習慣すらなく、自分が何者かも考えなかったのに、歳を重ねて、自分が自分と言えるようになる。
大学院で勉強に励む中、従軍するか大学に残るか考えあぐねるシーン:
内省に心を貸す習慣のまったくないストーナーにとって、自分の行動理由を吟味する作業は手ごわく、やや不快でもあった。自分自身に対して差し出せるものがほとんどなく、自分自身の中に見出せるものもほとんどないことを実感させられた。
(p.43)結婚後、新居でのシーン:
書斎の改造に取り組み、それが少しずつ形になっていくにつれて、もう何年も前から、自分の中の自分でも知らない一郭に、ひとつの心象風景が恥ずべき秘密のごとくしまい込まれていたことに気がついた。表向き、それはひとつの場所の風景だが、じつは自分自身の風景だった。つまり、ストーナーは書斎を整えながら、そうすることで自分自身の輪郭を定めようとしていたのだ。本箱用の古い板材に紙やすりをかけると、表面の粗い凸凹が消え、付着物の灰色の薄片が剥がれて、本来の木の面が現われ、やがて豊かで細やかな肌理が浮かび上がる。同じように、家具を修理し、それを部屋に配置することで、少しずつ自分自身の形が明らかになり、自分自身が一種の秩序を獲得して、自分自身であることが可能になってくる。
(pp.117-118)40代。英語講師キャサリンとの会話:
「わたしたちは少なくとも、自分自身であろうとしてここまで来た。お互い、そのことを、自分たちが何者であるかということを知っている」
(p.254)60歳手前の時期:
見よ、わたしは生きている!
(p.295)臨終の床:
柔らかさがストーナーを包み、四肢にけだるさが忍び込んでくる。ふいに、自分が何者たるかを覚り、その力を感じた。わたしはわたしだ。自分がどういう人間であったかがわかった。
(p.326)
ストーナーの師であるスローンは、南北戦争直前に生まれ、「人民の中の、けっして取り戻せない何かを殺してしまう(p.41)」世界を経験した。それゆえアメリカが大戦に参戦後、学者や学生が徴兵されること、犠牲になること、学問の世界が影響を受けることに激しく怒り、絶望した。スローンが教官室で自然死しているのが見つかったとき、ストーナーはこう言う。:
ウィリアム・ストーナーは、スローンが怒りと絶望に襲われて、みずから心臓を停止させたのではないかという思いをぬぐえなかった。自分を手ひどく裏切り、堪えがたい境遇に叩き落とした世間に対する愛と侮蔑の、最後の意思表示として。
(p.104)
死がその人の「最後の意思表示」だとしたら、ストーナーの臨終シーンは、シェイクスピアのソネット73番、および授業でのスローンからの質問に対する、ストーナーが人生を経て出した回答、というふうに読めると思った。
73番で、死の比喩に「晩秋~冬」、「暗い」「夜」の世界が用いられているのに対して、ストーナーの臨終は「晩春~初夏」、「明るい陽射し」の入る「午後」の時間帯である。73番が「眠る」のに対して、ストーナーは「眠りから覚める」。
重いものがまぶたを押していた。その力にわななきが生じた瞬間、ストーナーはぱっちりと目を見開いた。光が、午後の明るい陽射しが感じられた。まばたきをし、窓の外の青空を、そして日輪のまばゆいへりを、眺めるともなく眺めた。これが現実だ、と心に決めた。手を動かすと、動きにつれて、宙から舞い降りたような力が加わった。深呼吸をする。痛みが消えた。
ひと息ごとに力が増すように感じられた。肌が火照り、顔にかかる光と影の繊細な重みがわかるような気がした。ストーナーはベッドに身を起こし、半坐りの状態になって、背中を壁に預けた。これで室外が見渡せる。
長い眠りから覚めたような爽快な気分だった。いまは晩春か、もしくは初夏。外の様子から見て、初夏らしい。裏庭の楡の巨木は、みずみずしい緑の幕に葉を覆われ、かねて知る深く涼しい木陰を与えている。空気は濃く、その重みが草や葉や花の甘い香気を孕んで宙に漂っていた。ストーナーはもう一度、深く息を吸った。耳障りな呼吸音がして、夏の香気が肺に流れ込んだ。
と、同時に、体の奥で変化が起き、何かが妨げられて、頭を動かすことができなくなった。だがやがてそれは収まった。なるほど、こういうものか、とストーナーは思った。
(p.325)
73番の「残り火」と呼応するのは、陽光に照らされるストーナーの「赤い」著書だろうか。
ストーナーはテーブルの上の本の山の上から一冊を抜き取った。自分の著書だ。とうの昔に色あせ、すり切れたなつかしい赤い表紙を見て、ストーナーは笑みを浮かべた。
この自著が忘れ去られて久しいこと、何の役にも立たなかったことは、もうどうでもよかった。いつの時代であろうと、この本に価値があるかどうかは些末なことだ。古びた印刷物の中に自分を見出せるとも思っていなかった。しかし自分のごく一部が確かにそこにあること、これからも存在し続けることは否定できない。
(p.327)開いたとたん、本は自分のものではなくなった。ページを繰ると、まるで紙の一枚一枚が生きているように、指先をくすぐった。その感覚が指から、筋肉へ骨へと伝わっていく。ストーナーはそれをかすかに意識し、全身がその感覚に包まれるのを待った。
(p.327)
彼が燃やしたものは燃え尽きることなく、ストーナーの肉体と精神を含めて形を変え、本として残った。ストーナーのごく一部が確かにそこにあること、これからも存在し続けることは否定できない。
参考
Analysis of Shakespeare’s Sonnet 73 – That time of year thou mayst in me behold
http://www.shakespeare-online.com/sonnets/73detail.html